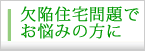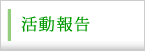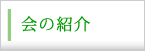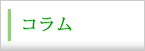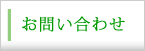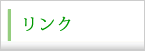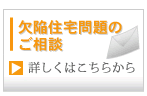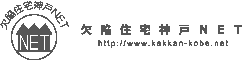 |
|

2018年(平成30年)11月18日、19日愛媛県松山市で開催された欠陥住宅被害全国連絡協議会に参加してきました。 今回の大会は、マンションの大規模修繕に関する建築士の関わり方、自然災害と住宅の安全、全国ネット110番の意義と課題、各ネットの判決・和解事例の報告が行われました。 中でも、自然災害と住宅の安全に関する報告とパネルディスカッションは、平成30年が例年にも増して台風や地震など自然災害の脅威にさらされた年だったこともあり、私にとって特に印象が残りました。 「住宅の安全」を擁護するためにどのような方法があるのか、自然災害によるものであるのか、住宅の欠陥に基づく人災であるのかを全国の有志とともに検討できました。この経験を踏まえ、自然災害が生じた際に業者側より主張される「不可抗力」という主張が、建物の基本的安全性を損なう欠陥住宅を建築・放置した者の免罪符とならないように適切な主張をしたいと思います。 そして、「住宅の安全」を消費者個人が当たり前に享受できる社会であることが必要であることを痛感するとともに、同社会の実現に向けて欠陥住宅ネットを通して活動して参ります。 以上 今回の大会は、民法改正と建築瑕疵担保責任、建築士業務をめぐる問題、欠陥住宅ネットの相談体制の現状と課題、各ネットの判決・和解事例の報告と多岐にわたる議論が行われました。 1日目の民法改正と建築瑕疵担保責任では、これまでの判例を検討することで、改正民法が規定する「契約の内容に適合しもの」という条文について深い検討・議論がなされたと思います。 また、2日目は、各地域ネットにおいて欠陥住宅被害の相談体制について活発な議論がなされました。住宅に対する不安を抱えている相談者の不安を一人でも無くすために、相談者がアクセスしやすい環境は何か、何ができるのかということを改めて考えさせられる契機となりました。 今回の大会は、上記のように欠陥住宅被害について救済の法的根拠となる条文、裁判例によって具体化された規範の検討及び欠陥住宅についての相談者の不安をどうすれば取り除くことができるのか、活発な議論がなされた有意義な大会でした。 今後は、全国大会で協議した内容をふまえ、欠陥住宅被害に取り組んでまいりたいと思います。 以上  平成29年5月27日(土),同年5月28日(日)に欠陥住宅被害全国連絡協議会第42回東京大会が開催され,私は,神戸ネットの一員として同大会に参加してきました。 初日は,特別報告として『東日本大震災をきっかけにスリット未施工等によりマンションが大破した事案』の報告があり,その後技術士・大学教授・弁護士等から『地盤の液状化に係る諸問題』について,講演・パネルディスカッションがありました。 まず,東日本大震災によりマンションが大破した事案の報告では,マンションの法律問題を検討する前に,マンション管理組合の理事の方が弁護士にアクセスするまでに様々な障害を持たれていることが分かりました。具体的には「理事として弁護士に法律相談に行くには,法律相談の費用の費用はどこから支出してよいのか迷った。どの弁護士に依頼したらよいのか判断が難しい」というものでした。普段,依頼者が弁護士事務所に来所していただいていますが,法律相談に来所される以前にも障害があることを実感させられました。 次に,液状化の問題については,液状化によって一生の買い物である住宅への影響に関して技術士・大学教授・弁護士から,詳細な説明がありました。中でも,東日本大震災を経験により,震度5程度の中地震により液状化が発生し,それによってベタ基礎の建物が傾く等の重大な被害が生じたことから,東日本大震災後に建築された建物の液状化被害が問題となる裁判では,販売時の液状化被害の予見可能性が認められやすくなることが予想されるとの報告がありました。液状化に対する予見可能性について否定的な裁判例が続く中で,今後の指針が示され有意義な講演となりました。 二日目は,『中古住宅にかかわる最近の状況と問題点』について,京都ネットより基調報告があり,その後,各ネットの『判決・和解事例報告』がありました。 各ネットの判決・和解事例報告を拝聴させていただくことで,専門家として建築訴訟を行う上での悩みや,各事例において工夫した点を共有させていただきました。もとより弁護活動は一つ一つの事案毎に処理方針は変わるものですが,上記各事例の報告でご教示いただいた様々な工夫は,個別性の高い事件処理を行う弁護活動においても,その活動をより良いものとするためのヒントが多数ちりばめられていたと思います。 今後は,第42回東京大会で獲得した知見を神戸ネットにおける活動に還元していきたいと思います。 建築基準法第7条に基づく完了検査率は、全国平均90%に高まった。80%台の県が残る一方、1・2・3・4号建築物ごとにみると、60以上の特定行政庁(全国に449)が100%若しくは、「概ね100%」の年度を経験している。増渕は形式知「完了検査率は必ず100%にできるという法則」が存在することを実証的に明らかにした。違反の事後的な回復は容易でないから、「完了検査率100%」の意義は大きい。庶民住宅の質的改善を図るべく米国のラス検査(中間検査と推測する)などを参考にして現場検査を盛り込んで建築基準法をつくった内藤亮一建築指導課長らの立法趣旨をかみしめる。
2015年(平成27年)5月30日,31日に岩手県盛岡市で開催された全国大会に参加してきました。
平成27年2月12日(土曜)に、広島市で開催された広島欠陥住宅研究会15周年記念行事に参加してきました。 平成26年11月22日(土)~23日(日)に、下関市において欠陥住宅被害全国連絡協議会(欠陥住宅全国ネット)下関大会が開催されました。
平成9年の年末、夜遅く大阪弁護士会館を後にして、帰路、暗い路地裏を萩尾利雄建築士と梅田に向って歩いていた。
㈱アーキノヴァ設計工房 柏本 保  昨年12月に知り合いのジャズメンの新譜のCDジャケットにはからずも私の拙いスケッチが採用される運びとなりました。事の発端は、昨年2月に甥が出入りしている“ライブ喫
茶”に立ち寄り、経営者夫妻を紹介された事によります。 昨年12月に知り合いのジャズメンの新譜のCDジャケットにはからずも私の拙いスケッチが採用される運びとなりました。事の発端は、昨年2月に甥が出入りしている“ライブ喫
茶”に立ち寄り、経営者夫妻を紹介された事によります。御夫妻は私とほぼ同年代であり、私より少し年下のママは現役のジャズシンガーで、団塊世代にはなつかしい“スクールメイツ”の第1期生、少し後輩の“スクールメイツ”出身で、一世を風靡した“キャンディーズ”の元メンバーで今年急逝したスーチャンより少し年上で同じステージに立っていたようです。口の悪いマスターによれば、“キャンディーズ”のなり損ない(?)とのことです。 若かりし頃のポピュラーソングの話題で盛り上がりましたが、その際毎月のライブにはなつかしの曲を演奏する私好みのいわゆる“大人のジャズトリオ”の出演もあるのでライブに是非立ち寄ってほしいとのことでした。その後毎月ライブの案内を頂いていたので、昨年6月19日の「204トリオ」というピアノ・ベース・ドラムスのジャズトリオのライブ演奏を聞きに初めて出向きました。このトリオの良さは、適度にムーディで、うるさ過ぎず、色々なジャンルの演奏を楽しめることにあります。計2時間半の2ステージ共ママのボーカルとのコラボが楽しめ、まさに大人のやすらぎのひとときを楽しむこととなりました。その際のママとのコラボの写真を2~3枚写真撮影したので、その写真を参考に4人のライブでの情景をスケッチし、次の月のライブで「204トリオ」とママに記念にプレゼントしました。 その後何度か出向きましたが数が月後、ママを通じて「204トリオ」のバンドマスターから、12月にレコーディングするCDレコードのジャケットにこのスケッチを使わせてほしいとの申し入れがありました。手前みそですが、バンドマスターの言によると、演奏中のご自身の表情がうまく表現されており、御本人が非常に気に入っているとの事でした。ただし、ただ一つ条件がありました。その条件とは、トリオの演奏のCDなので、センターポジションに鎮座ましますボーカルのママの姿を消してほしいというものでした。 幸い水彩画ですので、ボーカルのママを砂消しゴムで残酷にも消し込みました。ママの後ろに大半隠れていたベースの正面の再現には写真がなく骨が折れましたが、何とかごまかし、無事トリオのスケッチを完成しました。  私のスケッチは、まだ初めて2年足らず、はがき大に風景や建物、身の回りの物を素材に現在約120~130枚程度
書き貯めておりますが、今回は思いもよらない体験をし、ジャケットの評判、CDの売り上げ共上々のようで正直ほっとしております。
私のスケッチは、まだ初めて2年足らず、はがき大に風景や建物、身の回りの物を素材に現在約120~130枚程度
書き貯めておりますが、今回は思いもよらない体験をし、ジャケットの評判、CDの売り上げ共上々のようで正直ほっとしております。
仙台空港に着陸する際,以前は美しい防風林に覆われた海岸線を機内から望むことが出来たのですが,私の目に飛び込んできたのは,津波によりなぎ倒された木々の姿。 大津波の凄まじさに恐怖を感じました。 幹事会は,東日本大震災による大きな被害の一つである液状化現象についての勉強会から始まり,次いで11月の全国大会の概要を取り決め。2日目は,今回の震災により仙台市周辺において地盤被害に遭われた方々から被害状況等の聞き取りを行いました。 マスコミには,津波,原発問題が大きく取り上げられているが,地盤被害も深刻な被害であることを改めて認識しました。この聞き取り結果が,11月の全国大会に反映されればと思います。 今回の幹事会は,大震災という未曾有の災害に直面し,私たち弁護士は何が出来るの かについて考える機会を与えてくれた幹事会でした。 先日、建築確認手続き等の運用改善の係る講習会を受講してきました。 内容は、全体に耐震偽装事件で規則が強化されましたが、今度は、平成22年6月1日よりそれが緩和されます。 「小規模建築物(木造住宅等)」では、1、木造の四号建築物ついて①確認審査の迅速化 ②申請図書の簡素化 ③厳罰化 ④4号建築物に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。⑤既存不不適格建築物の増改築に係る特例の見直し(緩和処置)について、周知徹底を図る。です。 「一般建築物】では、①確認審査の迅速化 ②申請図書の簡素化 ③厳罰化です。 特に、小規模建築物(木造住宅等)の4号建築物に係る確認・検査の特例について、当分の間継続する。について、このたびは、特例が解除されると期待して、多種多様の講習会に参加して知識を入手しましたが残念です。私のように、欠陥住宅(全ての建築物)問題に取組んでいるものに執っては、このたびの改正で、欠陥問題の減少に前進が見えません。 このたびの改正は、設計者及び施工者の味方であり、建築主及び住宅購入者には、以前と変化はありません。 この前の建築士法の改正では、指定検査確認機関等は処罰を受けなく監督命令を受けるのみで、従事した建築士のみが処罰を受けます。 建築主及び住宅購入者は、耐震偽装事件で建築基準法等が強化されて安心と思われていると思いますが、自己責任という事を忘れずに、よい建築士等に相談され、建ててから、購入してから問題が発生しないように努めてください。 先日、ある講習会で欠陥建築問題に長年取り組んでこられたベテラン弁護士から面白い話を聞いた。
その家は、建売住宅だったが、売主の建築会社は倒産していたし、仲介をした不動産会社も 交渉中に倒産した。 建築確認を申請した建築士さんからいくらか回収できただけだった。 建物の欠陥がひどければひどいほど、損害賠償の回収も難しくなるという典型的な例だった。
建築家による工事監理においては、工務店が実施する工事の隅々まで見てもらえるものだと勘違いをされている人がいます。 建築家の工事監理は、工務店、職人の一挙手一投足をみるわけではありません。
監理者には、施工内容が設計図書どおりであるかどうかを確認することが監理業務の基本として求められています。確認するべき内容は、施工者が前もって検査をした内容であるべきなのです。施工途中の内容を確認するのでは、その後の工事により変更が生じた場合混乱するからです。 自主検査が出来ない施工者もあります、職人任せで工事を進めることも多いのです。 このような場合、監理者は直接職人と約束を交わすことが出来ない為、施工内容に関してもその確認作業に支障が出ることになります。 施工者の自主管理は非常に重要なのです。 監理者は、施工者の自主検査完了報告書を受け取った上で現場確認を行なうべきなのです。 | |
|
欠陥住宅神戸NET
|
|
![]()